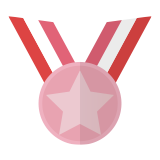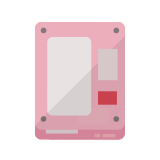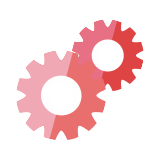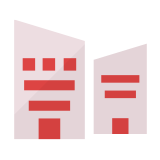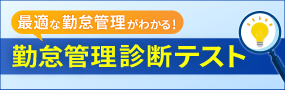コアタイムの意味・目的とは?フレックスタイム制度の役立つ基礎知識からコアタイムの設定における注意点などを解説
勤怠管理システム
ナレッジ

従業員のワークライフバランスを向上させるため、フレックスタイム制を採用する企業も増えてきています。ただ、フレックスタイム制は自由度の高い制度なだけに、企業側も従業員側もしっかりと理解したうえで採用する必要があります。
今回は、市場シェアNo.1の勤怠システムを提供するタッチオンタイムがフレックスタイム制の基本的な知識として「コアタイム」「フレキシブルタイム」という2つのポイントに絞って、詳しく見ていきましょう。
フレックスタイム制の採用を考えている人は、ぜひ参考にしてください。
目次
フレックスタイムの概要

フレックスタイムとは、「始業時間と終業時間を従業員自らが決めることができる制度のこと」をいいます。日本では、1987年の労働基準法改正に伴って、1988年より導入されました。
一般的には、会社が決めた始業時間、終業時間に従って、1日8時間働くというスタイルが主です。一方でフレックスタイム制は、勤務時間を1日単位ではなく「清算期間」と呼ばれる一定期間の総労働時間としてとらえ、1日の労働時間はある程度変動させて働くことができるという特徴があります。
ただ、フレックスタイム制を採用する企業のすべてが、完全に自由な勤務時間設定を認めているとは限りません。勤務時間を決定するうえで必要な「フレキシブルタイム」「コアタイム」という考え方について、次から詳しく見ていきましょう。
フレキシブルタイムの概要

フレキシブルタイムとは、従業員本人が自由に勤務時間を決定できる時間幅のことです。
例えば、6時から10時までが始業時間のフレキシブルタイムと設定されている場合、7時に出勤したとしても、9時に出勤したとしても問題ありません。この制度を利用すれば、出勤前に病院を受診することも、通勤ラッシュを避けて早めに出社することも可能になります。
ただ、始業時間と終業時間を決定する際に、清算期間の総労働時間は満たすように注意しなければなりません。自由が認められる一方で、従業員一人一人が、自らのスケジュールを管理する責任を持つことになります。
コアタイムの概要・意味・目的

コアタイムとは、1日のうちで必ず就業しなければならない時間帯のことを指します。フレックスタイム制において、コアタイムは必ずしも設定が義務付けられているわけではありません。
ただし、会議やチーム作業の予定が組みづらいという理由から、コアタイムを導入するスタイルが多いようです。
コアタイムの設定の仕方についても労使協定の中で合意済みであれば、自由に決めることができます。例えば、コアタイムは曜日によって時間帯を変えたり、1日の中で分割したりしても問題ありません。
実際には、作業のしやすさという理由から、フレックスタイムを採用する多くの企業が、人が比較的集まりやすい中間の時間帯をコアタイムとして設定しています。従業員の働き方にある程度の自由は認めつつも、職場内での連携をしっかりと保つためには、バランスよくコアタイムを設定する必要があります。
コアタイムの設定における注意点

コアタイムを設定する際には、以下の注意点があります。
- コアタイムの時間が従業員と会社の双方にとって適切
- コアタイムは日によって変えられる
コアタイムが長すぎれば、フレックスタイムの割合が短くなり従業員は自由な働き方がしづらくなります。逆に、コアタイムが短すぎると、他の従業員との連携がしづらくなります。そのため、従業員と会社の双方にとって働きやすい時間をコアタイムとして設定しましょう。
例えば、毎朝8時~9時をコアタイムにしてしまうと、毎朝8時に出勤することになるため、自由な働き方をしづらいです。逆に、13時~15時というように中間的な時間をコアタイムに設定すると早く出勤したい人と遅く出勤したい人の両方に都合が良いと言えます。
また、コアタイムは日によって変えることができます。例えば、月曜日は11時~13時がコアタイム、水曜日はコアタイムはなし、金曜日は15時~17時がコアタイムというように設定できます。
コアタイムは、従業員と経営環境を踏まえて設定をするのが望ましいです。
コアタイムにおける遅刻・早退・半休とは?

コアタイムに遅刻・早退・半休をした場合はどうなるのでしょうか?フレックス制は合計の労働時間で判断するため、コアタイムに遅刻・早退・半休をしても、1カ月の総労働時間を満たしていれば、基本的には減給はできません。
半休は仕方ないにしても、コアタイムに遅刻・早退が続くと、コアタイムの意味が無くなり、社内の秩序が乱れるリスクがあります。
そこで、コアタイムの遅刻や早退に対して、就業規則の制裁規定で減給処分を定めることは法律的に可能です。
他にもコアタイムへの遅刻・早退の有無を人事評価に取り入れるなどしてコアタイムの遅刻・早退を減らす仕組みを作っておくのが賢明です。
なお、半休を使ってコアタイムに出勤しないことは可能です。しかし、コアタイムは従業員同士が集まることを目的にしています。なので、やむをえない場合を除き、できるだけコアタイムには出勤してもらい、フレックスタイムの間で半休を取得してもらうのが望ましいです。
フレックスタイム制度のメリット・デメリット

フレックスタイム制度のメリットとデメリットをそれぞれ解説してきます。
従業員側におけるフレックスタイム制度のメリット
フレックスタイム制度のメリットは、以下の通りです。
- 通勤ラッシュを避けられる
フレックスタイムによって、出社の時間をずらして通勤ラッシュを回避することができます。通勤を苦に考える社員がいる場合、このようなストレスを軽減することができ、労働⽣産性の向上が期待できます。
- 仕事とプライベートの両立しやすくなる
あらかじめ働く時間の総量(総労働時間)を決めた上で、⽇の出勤・退勤時刻や働く⻑さを労働者が⾃由に決定することができるため、勤務時間に融通が効きます。
結果、仕事と育児や家事などのプライベートとの両立をしやすくなります。
企業側におけるフレックスタイム制度のメリット
- 従業員の採用率が上がりやすい
採用時に「フレックス制度を導入している」とアピールすることで、優秀な人材の採用率が上がりやすくなります。
- 従業員の定着率が上がりやすい
フレックスタイム制度を採用すると、育児・介護中の方でも自身にあった働き方が可能になります。さまざまな人が仕事を長く続けられるようになることで従業員の満足度が上がり、従業員の定着率も上がりやすくなります。採用コストや教育コストを抑えられるのがメリットです。
フレックスタイム制度のデメリットと対策
フレックスタイム制度のデメリットは、以下の通りです。
- 社内および社外のコミュニケーションに工夫が必要
従業員同士がコアタイム以外は、別の時間に勤務することが増えるため、従業員同士のコミュニケーションには、コアタイムの利用などの工夫が必要になります。情報の交換について、文書で行うなどの工夫を行うほか、Zoomやチャットなどのオンラインコミュニケーションツールを充実させることも大切です。
社外コミュニケーションにおいても、「担当者がつかまらない」といった不満が取引先から出ないように、社内体制に気を配る必要があります。
- 勤怠管理が複雑化しやすい
また、フレックスタイム制度は勤怠管理が複雑化しやすいというのがデメリットです。タイムカードなど、人力での集計は非常に困難になり、勤怠管理システムの導入が望まれます。
後ほど、多様化する働き方にあった勤怠システムをご紹介します。
フレックスタイム採用に必要な2つの要件

では、フレックスタイムの採用はどのように行えばいいのでしょうか?企業側は、フレックスタイム制を採用するに当たって、次の2点を満たしていることが必要です。
- 就業規則への明記
- 労使協定の締結
それぞれ解説していきます。
就業規則への明記
就業規則の中で、フレックスタイム制の採用(始業時間、終業時間の決定を従業員本人の決定に委ねること)をはっきりと明記しておきます。
労使協定の締結
労使協定の中で、フレックスタイム制の基本的な方針を明記しておく必要があります。この内容をもとに、従業員の過半数で構成される労働組合や、その代表者が決定を下します。ここで定めるべき基本的な項目については、次で詳しく見ていきましょう。
労使協定で定めるべき6項目

労使協定の中では、次の6項目について定める必要があります。
- 対象となる従業員の範囲
- 清算期間の長さ(3ヵ月以内)
- 清算期間の起算日
- 清算期間内の総労働時間
- 1日の標準労働時間
- コアタイム・フレキシブルタイム
詳細については、以下の表をご確認ください。
| 対象となる従業員の範囲 | まずは、対象者を明確にします。全従業員とする以外に、グループ単位、個人単位で定めることができます。 |
|---|---|
| 清算期間の長さ(3ヵ月以内) | 従業員の労働時間を定めるうえで基準となる期間の長さを定めます。 従来は労働基準法の中で規定されている通り、清算期間は1カ月以内で設定しなければなりませんでした。しかし、働き方改革関連法の制定により、清算期間が最長3カ月となりました。とはいえ、月をまたいだ労働時間の調整は管理が複雑となるため、注意が必要です。 |
| 清算期間の起算日 | 清算期間には、「毎月1日から」というような具体的な起算日が必要になります。 |
| 清算期間内の総労働時間 | 清算期間内で従業員が働く総労働時間を定めます。フレックスタイム制においては、この時間を満たすように始業時間と終業時間を決定する必要があります。 |
| 1日の標準労働時間 | 1日の標準労働時間は、フレックスタイム対象者が有給休暇を取得した際の措置です。労働時間が日によって変動するフレックスタイム制では、1日当たりの賃金も固定ではありません。1日の標準労働時間を定めておくことで、有給休暇を取得した際の賃金決定の基準とすることができます。 |
| コアタイム・フレキシブルタイム | 1日の中で、どの時間帯をコアタイム、またはフレキシブルタイムとするか定めます。この2つの時間帯のバランスによっては、従業員が時間を調整しづらくなったり、フレックスタイムと認められなかったりということにもなりかねないため、慎重に決定する必要があります。 |
フレックスタイム制における残業代に関する注意点

一般的な固定時間勤務制の場合は、会社が定めた終業時間を超えて作業した分が「残業」とみなされます。しかし、フレックスタイム制ではそのようには換算されません。
1日当たりの就業時間ではなく、あくまで清算期間ごとの総労働時間を超えたかどうかで残業時間が決定するため、注意が必要です。
総労働時間を超過して作業した場合は、その時間に見合う残業代が支払われることになります。この場合、超過した時間を次の清算期間の勤務時間として繰り越すということは認められないため、企業側は必ず清算期間ごとの残業代を支払う義務があります。
フレックスタイム制の清算期間の延長

フレックスタイム制の清算期間はもともとは1カ月でした。しかし、2019年4月に働き方改革関連法により、労働基準法が改正され、上限が3カ月に延長となりました。
例えば、いままでは、1か月間の総労働時間に満たなかった場合、欠勤になりました。しかし、3カ月単位では1カ月目で総労働時間に満たなかった場合でも、2カ月目や3カ月目に多く働くことで、1カ月目の不足分を相殺できるようになりました。
これにより、月をまたいでの労働時間の調整が可能となりました。そのため、より柔軟な働き方が可能となりました。
清算期間の延長による注意点

1カ月を超える清算期間のフレックス制度を導入する場合は、管轄の労働基準監督署へ労使協定を届け出る必要があります。届け出を行わないと罰則の対象となってしまいます。
以下の場合は、時間外労働としてカウントされます。
- ①清算期間の法定労働時間の総枠を超えて労働した場合
- ②1カ月ごとに、週平均50時間を超えた場合
清算期間を3カ月に延長する場合は覚えておきましょう。
フレックスタイム制度は公私のバランスが重要

フレックスタイムを採用するうえで注意すべきなのは、「コアタイム・フレキシブルタイムのバランスをどう考えるか」です。
従業員個人のための時間として活用できるのがフレキシブルタイムだとすれば、コアタイムは職場内でのコミュニケーションを取れる時間ともいえます。
「生産性のUP」と言われているフレックスタイム制度の導入には様々な準備が必要です。しかし、フレックスタイム制度の導入を進める人事担当の方が理解を深めていくことで、導入が進みます。
会社全体の効率をさらに上げていければ、より働きやすくなる会社ができるのではないでしょうか。
フレックスタイム制度にも対応するクラウド勤怠管理システム「タッチオンタイム」

フレックスタイム制度の導入にあたり、それに対応する勤怠システムの導入が必要不可欠となります。多様化する働き方に合った勤怠システムを選びましょう。
タッチオンタイムは、フレックス勤務制にも対応しており、コアタイムの設定やフレックスタイム制の清算期間の延長も可能です。
タッチオンタイムは市場シェアNo.1を誇っており、継続率も99.7%です。
また、タッチオンタイムは、有給管理や残業時間の見直し等働き方改革にも対応しており、万全なサポート体制を備えております。まずは、30日間の無料トライアルから始めてみてはいかがでしょうか?